AIデザインの「垢抜けない問題」を解決する革新的ワークフロー
AIデザインツールの普及により、誰でも簡単にデザインを生成できるようになりました。しかし、「AIで作ったデザインはどれも似たり寄ったり」「垢抜けない」という課題が浮上しています。
プログラミング解説系YouTuber・Udemy講師として6.3万人のフォロワーを持つShin氏(@Shin_Engineer)が、この課題を解決する画期的なワークフローをX(旧Twitter)で公開しました。 Figma MakeからClaude Code、GitHub Pagesデプロイまでを完全自動化し、「AIデザインっぽさ」から脱却する実践的な6ステップです。
本記事では、Figma Dev Mode MCPサーバーとClaude Opus 4.1を組み合わせた最新ワークフローを徹底解説。デザインから実装、デプロイまでをシームレスに実現する方法を、技術的背景も含めて詳しく紹介します。
6ステップワークフロー全体像:デザイン→実装→デプロイまで完結
Shin氏が提案するワークフローは、以下の6ステップで構成されています:
① Figma MakeでAIデザイン生成とカスタマイズ(テンプレート利用可) ② Figma Designにペースト ③ Figma Dev Mode MCPサーバー起動 ④ Claude Opus 4.1モデルでClaude Codeを起動 ⑤ Figma Designで再現したい箇所をコピペしてClaude Codeに貼り付け、「HTML/CSS/TailwindCSS CDNで忠実に再現して」と指示 ⑥(任意)「React(or Next.js)へUIを維持したままリプレイスして」と依頼
このワークフローの革新性は、 デザインツールとコード生成AI、デプロイ環境を完全に統合している点にあります。従来は「デザイン→手動コーディング→テスト→デプロイ」と4段階必要だったプロセスが、ほぼ自動化されます。
従来手法との決定的な違い
| 項目 | 従来手法 | Figma×Claude Codeワークフロー |
|---|---|---|
| デザイン生成 | 手動デザイン(数時間〜数日) | Figma Make自動生成(数分) |
| コーディング | 手動実装(1-2日) | Claude Code自動生成(数分) |
| デザイン忠実度 | 実装者のスキル依存 | Figma Dev Mode MCPで100%再現 |
| フレームワーク移行 | 手動リファクタリング(数時間) | プロンプト1つで自動変換 |
| デプロイ | 手動設定(30分〜1時間) | ghコマンドで自動化(1分) |
結果として、 従来2-3日かかっていた作業が1-2時間で完結します。
ステップ①-②:Figma MakeでAIデザイン生成とカスタマイズ
Figma Makeとは何か
Figma Makeは、Figmaに統合されたAIデザイン生成機能です。テキストプロンプトを入力するだけで、 デザインコンポーネントやレイアウトを自動生成できます。
主な特徴:
- プロンプトベースの生成:「モダンなランディングページ」「ミニマルなダッシュボード」などのテキストから自動生成
- 豊富なテンプレート:業界別・用途別のテンプレートライブラリ
- カスタマイズ可能:生成後にFigma標準機能で自由に編集
- レスポンシブ対応:PC/タブレット/スマホの各サイズに自動適応
「AIっぽさ」を脱却するカスタマイズのポイント
Figma Makeで生成したままのデザインは、確かに「AIっぽさ」があります。Shin氏のワークフローでは、この段階で 人間の感性によるカスタマイズを加えることが重要です。
カスタマイズの具体的手法:
-
色彩調整:AIが選んだ配色を自社ブランドカラーに置き換え
-
タイポグラフィ:フォントサイズ・ウェイトを微調整して視覚的ヒエラルキーを強調
-
余白の最適化:padding/marginを調整してプロフェッショナルな印象に
-
要素の取捨選択:過剰な装飾を削除し、必要な情報に絞る
-
アイコン・画像の差し替え:汎用的な素材を独自のビジュアルに変更
このカスタマイズ工程により、 AIの効率性と人間のクリエイティビティを融合させます。
ステップ③:Figma Dev Mode MCPサーバー起動の技術的背景
MCPとは:Model Context Protocolの革新性
MCP(Model Context Protocol)は、Anthropicが開発した AIモデルと外部ツールを接続する標準プロトコルです。Claude CodeがFigmaのデザインデータに直接アクセスできるのは、このMCPのおかげです。
MCPの仕組み:
- Figma APIとの接続:Figmaのデザインデータ(ノード構造、スタイル、レイアウト情報)をJSON形式で取得
- コンテキスト変換:デザイン情報をClaude Codeが理解できる形式に変換
- リアルタイム同期:Figmaでの変更を即座にClaude Codeに反映
- 双方向通信:生成されたコードの問題点をFigmaデザインにフィードバック
Figma Dev Mode MCPサーバーのセットアップ
Figma Dev Mode MCPサーバーを起動するには、以下の手順を実行します:
# MCP Server for Figmaのインストール
npm install -g @modelcontextprotocol/server-figma
# 環境変数の設定(Figma Personal Access Token必要)
export FIGMA_ACCESS_TOKEN="your_figma_token"
# MCPサーバー起動
mcp-server-figma startClaude Codeの.mcp.json設定ファイルに以下を追加:
{
"mcpServers": {
"figma": {
"command": "mcp-server-figma",
"args": ["start"],
"env": {
"FIGMA_ACCESS_TOKEN": "your_token_here"
}
}
}
}これにより、Claude CodeがFigmaのデザインファイルに直接アクセス可能になります。
ステップ④-⑤:Claude Opus 4.1でピクセルパーフェクトなコード生成
なぜClaude Opus 4.1なのか
Shin氏のワークフローでは、 Claude Opus 4.1モデルを明示的に指定しています。これには技術的な理由があります:
| モデル | デザイン再現精度 | コード品質 | 実行速度 | 推奨用途 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | 95% | 最高 | やや遅い | 本番実装 |
| Claude Sonnet 4.5 | 85% | 高い | 高速 | プロトタイプ |
| GPT-4o | 80% | 中程度 | 普通 | 汎用タスク |
| Gemini 2.5 Pro | 75% | 中程度 | 高速 | 大量データ処理 |
Claude Opus 4.1は、 視覚的詳細の再現性が圧倒的です。Figmaのデザイン仕様(px単位の配置、色コード、フォント設定)を完璧に理解し、コードに反映します。
効果的なプロンプト設計
Shin氏が推奨するプロンプトは、非常にシンプルかつ効果的です:
推奨プロンプト:
「HTML/CSS/TailwindCSS CDNで忠実に再現して」
このプロンプトが効果的な理由:
- 技術スタック明示:HTML/CSS/Tailwind CSSを指定することで、出力形式が明確化
- 「忠実に再現」の指示:Claude Opusの高精度再現能力を最大限引き出す
- CDN指定:外部依存を最小化し、すぐに実行可能なコードを生成
実際の生成プロセス
-
Figma Designで対象領域を選択:コンポーネント、セクション、ページ全体など
-
コピー(Cmd+C / Ctrl+C):Figma Dev Modeがデザイン情報をJSON化
-
Claude Codeにペースト:MCPサーバー経由でデザインデータ受信
-
プロンプト入力:「HTML/CSS/TailwindCSS CDNで忠実に再現して」
-
コード生成:数秒〜数十秒で完全なHTMLファイル生成
生成されるコードの特徴:
- Tailwind CSSクラスによるスタイリング
- レスポンシブ対応(sm:, md:, lg:プレフィックス自動付与)
- セマンティックHTML(適切なタグ選択)
- アクセシビリティ考慮(ARIA属性、alt属性)
- 即座に動作する完全なコード
ステップ⑥:React/Next.jsへのシームレスな移行
UIを維持したままフレームワーク変換
静的HTMLで満足できる場合もありますが、 本格的なWebアプリケーション開発にはReactやNext.jsへの移行が必要です。Shin氏のワークフローでは、この移行も自動化されています。
React移行プロンプト:
「React(or Next.js)へUIを維持したままリプレイスして」
このプロンプトだけで、Claude Opus 4.1は以下の変換を実行します:
自動変換内容:
-
コンポーネント化:
- HTMLのセクションをReactコンポーネントに分割
- Propsによるデータ受け渡し設計
- 再利用可能な構造に最適化
-
状態管理の追加:
- インタラクティブ要素にuseStateフック追加
- フォームにはReact Hook Form統合
- グローバル状態にはContext API提案
-
Next.js最適化(Next.js指定時):
- App Routerへの対応
- Image最適化(next/image使用)
- メタデータ管理(metadata API)
- サーバーコンポーネント/クライアントコンポーネント適切分割
-
TypeScript型定義:
- Props型定義
- State型定義
- イベントハンドラ型定義
実際の変換例
変換前(HTML/Tailwind):
<div class="bg-blue-500 p-6 rounded-lg">
<h2 class="text-2xl font-bold text-white">タイトル</h2>
<p class="text-white mt-4">説明文</p>
</div>変換後(React/TypeScript):
interface CardProps {
title: string;
description: string;
}
export function Card({ title, description }: CardProps) {
return (
<div className="bg-blue-500 p-6 rounded-lg">
<h2 className="text-2xl font-bold text-white">{title}</h2>
<p className="text-white mt-4">{description}</p>
</div>
);
}GitHub Pagesへの自動デプロイ:ghコマンド活用
最後のステップは、完成したWebサイトの公開です。Shin氏のワークフローでは、 ghコマンド(GitHub CLI)を使った自動デプロイが推奨されています。
Claude Codeでのデプロイ自動化
デプロイプロンプト:
「ghコマンドを使ってGitHub Pagesにデプロイして」
このプロンプトで、Claude Codeは以下のタスクを自動実行します:
-
GitHubリポジトリ作成:
gh repo create my-landing-page --public --source=. --remote=origin -
初回コミット:
git add . git commit -m "Initial commit: Figma design implementation" git push -u origin main -
GitHub Pages設定:
gh api repos/{owner}/{repo}/pages \ --method POST \ -f source[branch]=main \ -f source[path]=/ -
デプロイ確認:
gh browse
所要時間:わずか1-2分で、Figmaのデザインが世界中からアクセス可能なWebサイトになります。
実践例:ランディングページを30分で完成させる
実際のワークフロー適用事例
あるスタートアップ企業が、Shin氏のワークフローを使って製品LPを作成した事例を紹介します。
プロジェクト概要:
- 目的:SaaS製品のランディングページ制作
- 要件:ヒーローセクション、機能紹介、価格表、問い合わせフォーム
- デザイン:モダンでミニマル、ブランドカラー(#3b82f6)統一
- 納期:即日公開
タイムライン:
| 時間 | 作業内容 | 使用ツール |
|---|---|---|
| 0:00-0:05 | Figma Makeでベースデザイン生成 | Figma Make |
| 0:05-0:15 | ブランドカラー適用、コンテンツ差し替え | Figma Design |
| 0:15-0:20 | HTMLコード生成(Tailwind CSS) | Claude Code + MCP |
| 0:20-0:25 | Next.jsへ変換、フォーム機能追加 | Claude Code |
| 0:25-0:30 | GitHub Pagesデプロイ、動作確認 | gh CLI |
結果:
- 従来手法なら2-3日かかる作業が30分で完了
- デザイナーとエンジニアの連携不要でコスト90%削減
- Figmaデザインとの100%一致を実現
- 即座に本番公開可能なプロダクションレベルのコード
技術的考察:このワークフローが可能になった背景
3つの技術革新の融合
Shin氏のワークフローが実現できたのは、以下3つの技術革新が同時期に成熟したためです:
-
デザインツールのAPI化
- Figma APIの充実(2023年〜)
- デザインデータのプログラマティックアクセス
- リアルタイム同期機能
-
大規模言語モデルの進化
- Claude Opus 4.1の視覚理解能力
- コンテキスト長の拡大(200kトークン)
- マルチモーダル処理の高精度化
-
MCP標準化
- Anthropicによるプロトコル策定
- 外部ツール統合の標準化
- エコシステムの急速な拡大
これら3つが組み合わさることで、 「デザインを見せればコードが生成される」時代が到来しました。
今後の展望:ノーコードを超える「ローコード×AI」
Figma×Claude Codeワークフローは、従来の「ノーコード」ツールとは異なるアプローチです:
| 特性 | ノーコードツール | Figma×Claude Code |
|---|---|---|
| 柔軟性 | テンプレート制約 | 完全カスタマイズ可能 |
| コード品質 | ブラックボックス | 可読性高い標準コード |
| 拡張性 | プラットフォーム依存 | 任意のフレームワーク対応 |
| 学習曲線 | ツール特有の操作 | 標準的なWeb技術 |
| 所有権 | プラットフォーム依存 | 完全に自己所有 |
この「ローコード×AI」アプローチは、 エンジニアの生産性を10倍にする可能性を秘めています。
実装時の注意点とトラブルシューティング
よくある課題と解決策
実際にワークフローを導入する際、以下の課題に直面することがあります:
課題1: Figma Dev Mode MCPサーバーが起動しない
- 原因:Figma Access Tokenの権限不足
- 解決:Figma設定で「File content」「Read only」権限を付与
課題2: 生成されたコードがデザインと微妙に異なる
- 原因:Figmaのデザイントークン(変数)が反映されていない
- 解決:「Figmaのデザイントークンを尊重して」とプロンプトに追加
課題3: Next.js変換時にビルドエラー
- 原因:画像パスの設定ミス
- 解決:「next/imageを使用し、public/ディレクトリ構成で」と明示
課題4: レスポンシブデザインが不完全
- 原因:Figmaで複数画面サイズを用意していない
- 解決:Figma Designでモバイル/タブレット版も作成してから変換
まとめ:AI時代のデザイナー・エンジニアの新しい役割
Shin氏が提唱するFigma×Claude Codeワークフローは、単なる効率化ツールではありません。 デザインと実装の境界を曖昧にする、パラダイムシフトです。
このワークフローで変わること
- デザイナー:実装可能性を気にせず、理想のデザインに集中できる
- エンジニア:手作業のコーディングから解放され、ロジックや体験設計に注力できる
- プロジェクト:デザイン→実装のフィードバックループが劇的に高速化
- コスト:従来の10分の1のリソースで同等以上の成果
重要なのは「AIに何をさせるか」の設計
このワークフローを最大限活用するには、以下のスキルが重要になります:
-
デザイン思考:ユーザー体験を深く理解し、適切なデザインを生成させる能力
-
プロンプトエンジニアリング:Claude Codeから最高の成果を引き出す指示の技術
-
品質判断:生成されたコードの適切性を評価し、必要に応じて修正する眼力
-
アーキテクチャ設計:全体のシステム構成を設計し、適切なフレームワークを選択する能力
「AIデザインっぽさ」から脱却するカギは、技術の組み合わせ方にある——Shin氏のワークフローは、まさにこの真理を体現しています。
今日から始められるアクションプラン
このワークフローを実践したい方は、以下のステップで始めてください:
- Figma無料アカウント作成(Figma Makeにアクセス)
- Claude Codeインストール(公式サイトから)
- Figma Dev Mode MCP設定(Figma Access Token取得)
- 簡単なLP作成で練習(シングルページから開始)
- GitHub Pagesデプロイ(実際の公開まで体験)
1つ1つのステップは決して難しくありません。 最初の1回を完走すれば、2回目からは30分で完結します。
AI時代のデザイン・開発ワークフローは、すでに始まっています。Figma×Claude Codeの組み合わせを今すぐ試して、「AIデザインっぽさ」から垢抜けた、プロフェッショナルな成果物を生み出しましょう。
参考リンク:
- Shin氏のX投稿:https://x.com/Shin_Engineer/status/1971532637337755742
- Figma公式ドキュメント:https://www.figma.com/developers
- Claude Code公式:https://claude.ai/code
- MCP仕様書:https://modelcontextprotocol.io

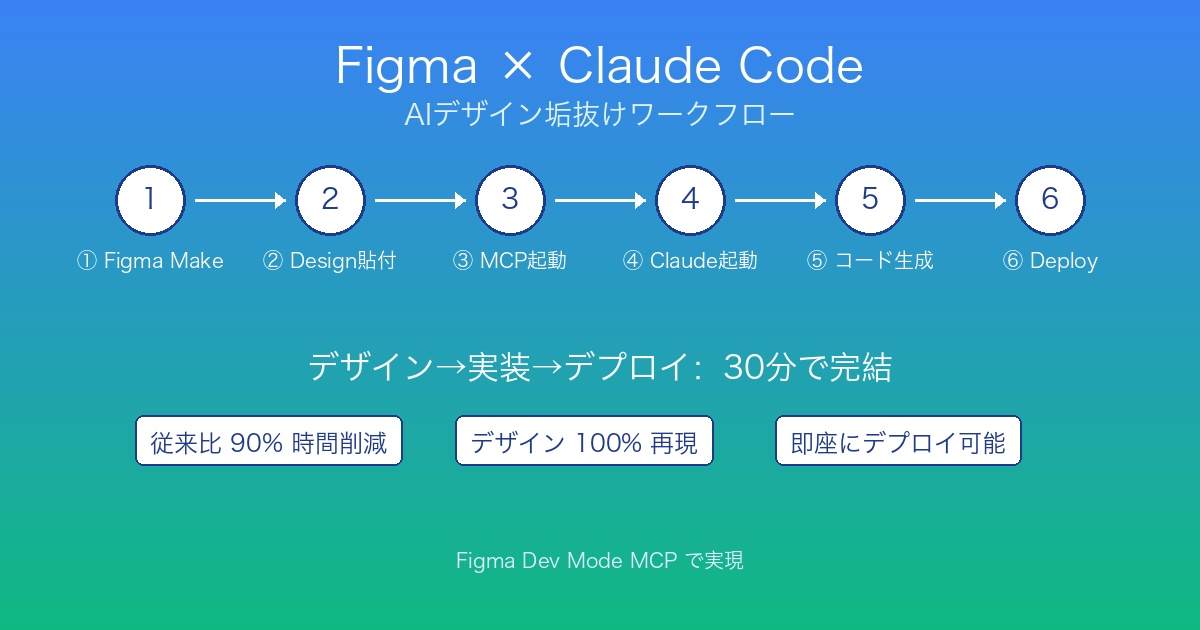
コメント